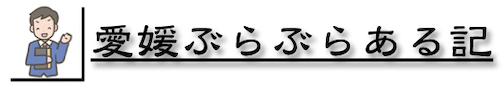Teacher
Teacher
皆さんは下の写真の場所を訪れたことはありますか?「札之辻」と刻まれた石碑が2種類建てられている場所です。
 昭和60年建立
昭和60年建立
 昭和46年建立
昭和46年建立
 Teacher
Teacher
左側写真に写っている「里程」碑の裏面に、札之辻の由来が刻まれています。
札之辻の由来
松山札之辻は、松山城と大林寺(城主代々の墓所)を結ぶ紙屋町の通りと、江戸時代松山随一の繁華街であった本町通りとの交差点にあたり、当時松山藩の制札所(高札場とも言う)のあった所で、伊予国の交通の起点となっていた。「松山叢談」によれば、ここから五大街道の里程が始まる。
「松山札之辻より何里」の石の里程標は、寛保元年(1741年)松山藩主第六代松平定喬公の時に、祐筆の水谷半蔵に書かせたものと伝えられている。
いま里程標は、各街道に合計三十数本が残存している。
昭和60年10月 建設省 松山工事事務所
(社) 四国建設弘済会
 Teacher
Teacher
上の写真にも写っていますが、松山札之辻を出発点とする各街道の名称と各地点までの距離を以下に記します。
金毘羅街道 小松まで十一里 金毘羅まで三十一里
土 佐 街 道 久万まで六里 土佐まで二十五里
大 洲 街 道 中山まで七里 大洲まで十三里
今 治 街 道 北条まで四里 今治まで十一里
高 浜 街 道 三津まで一里 高浜まで二里
 Teacher
Teacher
「札之辻の由来」にもある通り、ここを起点に延びた街道沿いには、道路の方向や距離などを示すため、一里〔約4km〕ごとに「里塚石〔りつかいし〕」が建てられました。この石が昭和60年当時、30数本残存しているというのです。
 「松山藩道路元標」と刻まれている
「松山藩道路元標」と刻まれている
 Teacher
Teacher
これは、その里塚石を求めて探索した記録です。里塚石が置かれた場所だけでなく、里塚石付近に残る史跡も紹介していきます。第3回は松山市から久万高原町を経て高知県へ向かう土佐街道を巡ります。松山藩は土佐街道筋に12基の里塚石を設置しました。その場所を地図で確認しましょう。
 Teacher
Teacher
里塚石が置かれた場所について、『松府古志談』の記述が『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』に引用されています。
- 一里 … 久米郡尼山村 (現松山市天山)
- 二里 … 浮穴郡森松村 (現松山市森松町)
- 三里 … 浮穴郡荏原村 (現松山市恵原町)
- 四里 … 久万山馬次九谷村(現松山市久谷町)
- 五里 … 同窪野村之桜休場(現松山市窪野町)
- 六里 … 同東明神村 (現久万高原町東明神)
- 七里 … 同久万町村 (現久万高原町入野)
- 八里 … 同菅生村 (現久万高原町菅生)
- 九里 … 同有枝村 (現久万高原町有枝)
- 十里 … 同七鳥村 (現久万高原町七鳥)
- 十一里 … 同東川村 (現久万高原町東川)
- 十二里 … 同縮川村 (現久万高原町黒藤川)
 Teacher
Teacher
これらの里塚石は山中奥深い所にあるものもあり、全ての里塚石を撮影できておりません。ですので、写真を掲載しているものとそうでないものがあることをご理解ください。土佐街道編第3回は、久万高原町内にある「六里」から「十二里」までの七基の里塚石を紹介していきます。それでは始めましょう!
【参考資料】ブログ「四国の古道・里山を歩く」土佐街道を歩く/『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』/「旧土佐街道の紹介」ホームページ(久万高原遊山会編)
「松山札辻より六里」里塚石
 Teacher
Teacher
まず最初に、土佐街道と国道33号との交差点を確認します。撮影していますので、写真をご覧ください。
 土佐街道〔左〕と国道33号〔右〕との交差点
土佐街道〔左〕と国道33号〔右〕との交差点
 Teacher
Teacher
この場所は、かつて伊予鉄道が経営していた「伊予鉄三坂峠ドライブイン」があった辺りです。この場所を地図で確認しましょう。
 Teacher
Teacher
「伊予鉄三坂峠ドライブイン」は昭和41〔1966〕年に開業しましたが、平成10〔1998〕年に高知道が開通すると松山-高知間の交通の大部分がそちらに移って客数が激減し、平成12〔2000〕年に廃業しました。現在跡地は雑草が生い茂り、入り口付近の桧垣伸翁碑のみが寂しく建っています。
 伊予鉄三坂峠ドライブイン跡地と桧垣伸翁碑
伊予鉄三坂峠ドライブイン跡地と桧垣伸翁碑
【参考】「廃線隧道【BLOG版】国道440号線・三坂峠② ※ 在りし日のドライブインの写真が掲載されています。
 Teacher
Teacher
嘉永3年~大正13年(1850~1924)県官。上浮穴郡郡長として郡内の開発に当たった。嘉永3年9月18日、松山藩士野田惟徳の次男に生まれた。幼名友諒。安政6年9歳のとき、桧垣家の養子となった。慶応2年藩校明教館に入学、明治2年同館助教を命ぜられた。4年学術修行のため高知藩に留学、5年松山の啓蒙学校校長を拝命、8年学区取締となり、9年愛媛県師範学校創立事務長、続いて同校監事を務めた。明治11年12月県令岩村高俊に抜擢されて下浮穴郡長に任じ、12年伊予郡長を兼任した。14年上浮穴郡長に転任、以後27年まで同郡長に在職した。
就任早々、旧藩時代以来の天災飢饉に備えての備荒儲蓄制度を継続し、これの維持方法として23年久万凶荒予備組合を組織した。ついで上浮穴の開発は道路の整備にありとして、梅木正衛らと図って三坂峠開さくの実現を県に運動した。これが、県令関新平を動かし、高知-松山間の「四国新道」開さく計画に発展した。明治19年工事が始まると、郡民の夫役を供出して全面的に協力、20年三坂峠の開さく完工に導いた。ついで四国横断鉄道敷設運動を始め、郡長退職後もこれを生涯の念願として各方面に説いた。大正9年横断鉄道陳情で上京の帰途大阪で罹病、13年11月15日、74歳で没した。久万町真光寺に葬られ、上浮穴郡の発展のため捧げた生涯をたたえて三坂峠の頂上に頌徳碑が建てられた。
『愛媛県史 人物』
 Teacher
Teacher
高知-松山間の道路開削等に貢献した方なのですね。さて、土佐街道に話を戻しましょう。最初に土佐街道と国道33号との交差点の写真を見ていただきましたが、もしかしたらこの場所ではなく、ここから少し東へ進んだ所が実際の土佐街道かもしれません。古い遍路道標が国道傍に建てられており、その向かいに山中へ入る細道がありました。現地で撮影した写真をご覧ください。
 古い遍路道標がある細道
古い遍路道標がある細道
 左写真の向かい側
左写真の向かい側
 Teacher
Teacher
ここから山中に入るため、私自身この道を進んでおりません。ですので、本稿においては土佐街道のルート紹介はやめ、里塚石の場所のみを地図で確認しながら記述していきたいと思います。久万高原町内の土佐街道のルートについては、平成22〔2010〕年に久万高原遊山会の方々が久万高原町教育委員会の委託を受けて調査し、その成果をホームページにまとめておられます。リンクを添付しますので、そちらでご確認ください。
【参考】「久万高原遊山会 旧土佐街道の紹介」ホームページ
 Teacher
Teacher
それでは里塚石の紹介に移りましょう。「六里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より六里」は国道33号の、東明神バス停の西方300mの旧道に立派に残っている。このあたりで標高560mで、標石のすぐ近くに常夜燈もある。六里の標石の大きさは、高さ230cmと幅19.5cmと奥行15.5cmである。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
『愛媛県史』の記述通り、「六里」里塚石は同じ場所にまだ残されていました。
 「松山札辻より六里」里塚石
「松山札辻より六里」里塚石 「六里」里塚石が建つ旧道
「六里」里塚石が建つ旧道 「六里」里塚石と常夜燈
「六里」里塚石と常夜燈
 Teacher
Teacher Teacher
Teacher
私は自転車で現地を走ってみました。細い道ばかりですので、自動車では絶対に行かないようにしてくださいね。
「松山札辻より七里」里塚石
 Teacher
Teacher
「七里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
七里の標石は、国道33号の、バス停の藤の棚と久万中学校前の中間にある。民宿の一里木の前にあり、標石の大きさは170cmと19.5cmと15cmである。注意しておればバスの窓から東側に見ることができる。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』
 「松山札辻より七里」里塚石と民宿「一里木」
「松山札辻より七里」里塚石と民宿「一里木」
 Teacher
Teacher Teacher
Teacher
「六里」里塚石から「七里」里塚石までの間に、紹介しなければならない史跡があります。「仰西渠」です。
仰西渠
 仰西渠之碑〔国道33号沿いに建てられている〕
仰西渠之碑〔国道33号沿いに建てられている〕
 Teacher
Teacher
碑の傍に建てられた解説板に「仰西渠」が造られた経緯が記されています。
 「仰西渠」解説板
「仰西渠」解説板
 Teacher
Teacher
「仰西渠」とは、山之内仰西によって造られた用水路なのですね。農業用水確保のために築造され、現在もその目的を果たし続けています。「仰西渠」を撮影しましたので写真をご覧ください。


【参考】農林水産省ホームページ 久万盆地に農業用水を引いた山之内彦左衛門 ※ トンネル内部の写真が掲載されています。
 Teacher
Teacher
次に、山之内仰西という人物の業績について紹介します。
生年不詳~元禄11年(~1698)江戸中期の商人。本名山之内彦左衛門光実、号は仰西という。国道33号を松山から高知に向かうと久万町の少し手前に「仰西渠」という用水路がある。ここは久万川の上流、天丸川に沿った安山岩の岩裾を掘削したもので長さ57メートル(うち12メートルはトンネル)幅2.2メートル、深さ1.5メートルで、上手は川水を取り入れ下手は田の用水路に結び入野村久万町村25町歩の水川を養っている。山田屋彦左衛門(山之内姓)が私財を投じて開削したもので、名称は彼の晩年念仏行者として仰西と号したことによる。久万町村は用水源に乏しく西明神村の天丸川に堰し何十もの樋をつないで水を引いていたが支柱の足場が悪いため、洪水のたびに樋が押し流され、そのたび人夫を動員してかけ替えねばならなかった。彦左衛門は恒久策を講じて農民たちを救いたいと考え、途中にある岩盤を掘りぬく工事を計画した。多くの人夫を雇い、石鑿の屑一升と米一升の引換えで賃銭を与え、自らも工事の先頭に立った。岩肌を軟らげるため乾した竿の茎を焼いたという話も伝わっている。工事はすべて彦左衛門の私財によったため成就するまでの3年間に豊かだった家も倒産したという。現在久万町にある法然寺も彼の建立といわれ、公共事業としては外に三坂峠の鍋割の険また落合の切石の難所の改修を行っている。文化3年(1806)の五代山田彦左衛門覚書に「開鑿年代は相分り難く候得共凡百三十余か年に相成り」と記してあるので延宝(1673~1681)の頃かと思われる。昭和25年に県指定史跡となり、碑文のある丘の足もとに用水が流れている。元禄11年1月26日、死去。
『愛媛県史 人物』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
地元住民の生活向上について尽力された方なのですね。注目したいのは太字にした部分です。彼は三坂峠の改修も行っています。「鍋割の険」とは三坂峠の難所で、足を滑らせたお遍路さんが背負っていた自炊用の鍋を割ってしまったことから鍋割坂とも称され、現地には碑が建てられています。
【参考】ブログ「坂道散歩」四国遍路道(愛媛県-7) ※ 「鍋割坂 仰西翁偉績」と刻まれた碑の写真が掲載されています。
 Teacher
Teacher
次に「落合の切石」とは土佐街道上に開いた切通しの道のことです。こちらにも碑が建立されているようです。機会があれば、現地を訪れてみたいですね。
【参考】ブログ「廃線隧道【BLOG版】」旧国道33号線・露峰の切石道 ※ 「切石 仰西翁偉績」と刻まれた碑の写真が掲載されています。
 Teacher
Teacher
これらの事業を私財を投じて行った山之内仰西という人は本当に慈愛に満ちた人物ですね。彼の業績を後世に伝えるため、久万中学校前には頌徳碑が建てられています。
 山之内仰西翁頌徳碑〔久万中学校前にて撮影〕
山之内仰西翁頌徳碑〔久万中学校前にて撮影〕
 Teacher
Teacher
以上で「仰西渠」及び山之内仰西についての紹介を終わります。次は「八里」里塚石です。
「松山札辻より八里」里塚石
 Teacher
Teacher
「八里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より八里」の標石は、昭和43年(1968)までは、久万川の左岸の宮前から、有枝川の右岸の上谷に至る、はしがみ峠(標高600m)に立っていた。昭和43年ころ、テレビ塔の工事のとき倒れた。しばらく久万町役場の軒下に持ち帰っていた。標石の大きさは180cmと18.5cmと15.5cmの安山岩である。はじかみとは山椒のことで、恐らく山椒の木が多かったのであろう。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
「八里」里塚石は最初はしがみ峠に建てられたということですが、現在は「越ノ峠」にあります。
 「松山札辻より八里」里塚石
「松山札辻より八里」里塚石
 Teacher
Teacher
「八里」里塚石は、県道153号から林道に入って100mほど登ったところにあります。その場所を地図で確認しましょう。
 Teacher
Teacher
「八里」里塚石は「林道宮の前・落合線」の案内板のすぐ近くにあります。県道153号からここまでの風景を撮影した写真を撮影順に並べてみました。もし訪れる際には参考にしてください。
 国道153号から林道への入り口
国道153号から林道への入り口 林道
林道 「林道宮の前・落合線」案内板
「林道宮の前・落合線」案内板 案内板と「八里」里塚石
案内板と「八里」里塚石 「越ノ峠」から「はじかみ峠」へ
「越ノ峠」から「はじかみ峠」へ
「松山札辻より九里」里塚石
 Teacher
Teacher
「九里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より九里」の標石は、程野部落に近い色ノ峠の西斜面で、峠から300m西の標高600mの杉林の中に立っている。「松山札の辻より」までが地上に出ていて、下は埋もれている。大きさは115cmと18cmと16cmで、安山岩である。今は人通りの少ない旧道である。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
「九里」里塚石は現在も「色ノ峠」にあります。『旧土佐街道の紹介』ホームページによれば、平成22年の調査の際に根元が折れて倒れていたのを久万高原遊山会の方々が建て直したそうです。
 撮影完了後、掲載いたします
撮影完了後、掲載いたします
【参考】『旧土佐街道の紹介』ホームページ 九里石 ※ 「九里」里塚石の写真が掲載されています。
 Teacher
Teacher「松山札辻より十里」里塚石
 Teacher
Teacher
「十里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より十里」の標石は、美川村大字七鳥にある東光寺の西方80m、旧道の山の側に立っている。下を面河行の県道が通っており、松岡ガソリンスタンドの上にある。標石の大きさは190cmと18.5cmと15cmである。この標石は十里の里の字が欠げて、十一里のように見える。旧道は、このあたりは平坦で、道幅も1m近く、草も余り生えておらず、昔の面影がある。ここから土佐街道は面河川を渡って、二箆の集落に上る。十里の標石のある地点の標高は400mであるのに対して、十一里の簑川の標石は標高880mの山腹にある。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
「十里」里塚石は現在も久万高原町七鳥の同地にあります。
 「松山札辻より十里」里塚石
「松山札辻より十里」里塚石
 Teacher
Teacher Teacher
Teacher
「九里」里塚石から東光寺までの土佐街道の現況を撮影しました。撮影順に並べましたのでご覧ください。
 奥が「九里」里塚石方面
奥が「九里」里塚石方面 常夜燈と「十里」里塚石
常夜燈と「十里」里塚石 「十里」里塚石から「十一里」方面へ
「十里」里塚石から「十一里」方面へ 東光寺へ①
東光寺へ① 東光寺へ②
東光寺へ② 東光寺へ③
東光寺へ③
 Teacher
Teacher
ちなみに、県道212号から東光寺への入り口はここです。
 東光寺参道
東光寺参道
 Teacher
Teacher
東光寺前を過ぎると土佐街道は七鳥バス停付近で県道212号に合流し、面河川へと続く細道へと続きます。


「松山札辻より十一里」里塚石
 Teacher
Teacher
「十一里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より十一里」の標石は、テレビ塔の標高948.5mの山頂より北方300mの林道に「天下泰平」の頌徳碑があり、この大正8年(1919)8月15日に建てた立石から、東方へ100mほど下った杉山の中に建っていた。筆者は十里から十一里への旧道を歩かず、美川村教育委員会の田中盛重主任の車で、御三戸から迂回し、二箆小学校の前からテレビ塔に出て十一里の標石に辿りついた。案内者がないとわからない。標石の大きさは175cmと19cmと17cmであった。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字は引用者による
 Teacher
Teacher
「十一里」里塚石は『愛媛県史』の記述と同じ場所に建てられていました。しかし、国道440号からかなり離れた場所にあり、現地に到達するまでかなりの距離の県道・林道を走り続けたので、腰が痛くなりました。疲れた❗️まずは里塚石の場所を地図で確認しましょう。
 Teacher
Teacher
御三戸嶽〔軍艦岩〕から国道440号を南進し、面河川を渡って県道210号〔美川川内線〕に入ります。県道を暫く進むと二箆〔ふたつの〕集落に県道と「十一里」里塚石へと向かう林道との分岐点があるので、そこから林道を進むと、『愛媛県史』の記述にあった「天下泰平」の頌徳碑前に到着します。
 「天下泰平」の頌徳碑と土佐街道
「天下泰平」の頌徳碑と土佐街道
 Teacher
Teacher

 Teacher
Teacher
この場所から見た風景はなかなか素晴らしいもので、いつの間にか腰の痛みを忘れていました。
 「天下泰平」の頌徳碑から見た風景
「天下泰平」の頌徳碑から見た風景
 Teacher
Teacher
「十一里」里塚石は、頌徳碑から林道に入って100mほど進んだ所にありました。
 「松山札辻より十一里」里塚石
「松山札辻より十一里」里塚石
 Teacher
Teacher 「十里」里塚石方面
「十里」里塚石方面
 「十二里」里塚石方面
「十二里」里塚石方面
 Teacher
Teacher
歩けるとはいえ、本当に山道でした。この道を抜けると、先ほどの頌徳碑の所に出ます。
 土佐街道と頌徳碑
土佐街道と頌徳碑
 Teacher
Teacher
ここを左折し、再び林道に入って暫く進むと、「十二里」里塚石及び高知県との県境です。
「松山札辻より十二里」里塚石
 Teacher
Teacher
「十二里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』は次のように記載しています。
「松山札の辻より十二里」の標石は、地形図の猿楽石のある標高1090mの旧道に立っている。このあたりはもっぱら尾根の道であるが、山仕事の人のほかは、旅人は全く歩かない山道である。猿楽石は4mに5mぐらいの一枚岩で、猿が集まって踊りをしたという伝説がある。標石のすぐ北側に、三間に二間半の営林署の山小屋があった。大師堂には弘法大師・薬師如来・成田不動を祭っており、つづら(くさかんむりに縮)川部落の正泉寺の出張所で、昭和34年と同47年に修理している。ここから西方2㎞に「盗人石」という5mに3mに1.2mの巨岩がある。石鎚山の賽銭を盗んだ男が天狗につかまり、落ちて石になったという伝説がある。猿楽石の十二里の標石から約2㎞東が県境で、舟形の天保12年に建てた石像が二基あった。大きさ46mと25cmと10cm、40cmと25cmと10cmで、国境碑はなかった。
『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』 ※ 太字及び下線は引用者による
 Teacher
Teacher
「十二里」里塚石について、『愛媛県史 地誌Ⅱ(中予)』と同じ場所にあるようですが、残念ながら私はまだ訪れておりません。
 撮影完了後、掲載いたします
撮影完了後、掲載いたします
 Teacher
Teacher
「十二里」里塚石の場所を地図で確認しておきましょう。里塚石の写真については、「旧土佐街道の紹介」ホームページの該当箇所のリンクを添付しますので、そちらでご覧ください。
【参考】「旧久万街道の紹介」ホームページ 十二里石
 Teacher
Teacher
以上で、松山藩が土佐街道筋に建てた十二基の里塚石の紹介を終わります。現段階では中途半端な内容なので、「土佐街道を歩く」等のイベントがあれば参加して「九里」及び「十二里」里塚石を撮影したいと思います。ここまでご一読いただき、ありがとうございました。
⇦ Forward.土佐街道編②
関連