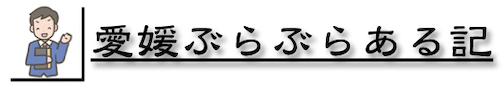松山電気軌道の廃線跡をたどろう!⑤ 八股〜六角堂


今回は、八股停留所から六角堂停留所までの廃線跡をたどりましょう。この区間は、松電の路線を伊予鉄道が活用しているだけでなく、かつての軌道跡が道路としてはっきりと残されている区間です。

以前、正岡子規の『散策集』のところで学びました。一番町から松山東警察署までの斜めの道ですよね。
【参考】正岡子規『散策集』吟行の道をたどろう!道後湯之町へ①

よく覚えていましたね。もう一度地図で廃線跡を確認しましょう。


松電の電車は、八股停留所を出発して現在の一番町通りを東進し、この道を斜めに北上したんですよね。

その通りです。この廃線跡を昭和22〔1947〕年に米軍が撮影した航空写真で確認してみましょうか。


廃線跡がはっきりと分かりますね。伊予鉄道が吸収合併した道後鉄道の線路跡もよく分かります。

では次に、八股停留所-六角堂停留所間を拡大してみましょう。現在の地図と異なるところを見つけてください。


現在と違うところ…、どこだろう?

松電の廃線跡をたどりながら、建物ではなく道を見てください。

道ですか?現在松山地方検察庁の建物がある辺りが緩やかにカーブしているように見えますね。

【参考】ブログ「EEKの紀行 春夏秋冬」昭和20年7月26日、松山大空襲 ※ 2枚目の写真に注目!

Takashi君、さすがです。それでは、各停留所付近の歴史について説明しますね。

はい。お願いします。
① 八股停留所付近 〜松山中学校跡の変遷〜

八股停留所は伊予鉄道城南線の市役所前駅とほぼ同じ場所にあり、昭和19〔1944〕年に現在の駅名に改称されました。
【参考】廃線隧道【BLOG版】松山電気軌道⑤【八股〜一番町】 ※ 八股停留所付近の写真が掲載されています。

停留所の西には松山城の堀、北には松山城天守閣が見える絶好の撮影スポットでもありますよね。

市役所前駅正面の堀端沿いに、川東碧梧桐の句碑が建てられていますよ。


この句碑は、入所者の情操教育を目的として、松山刑務所内に昭和7〔1932〕年に建立されたと言われていて、昭和28〔1953〕年に当地に移設されたものです。

この句碑にはそんな歴史があったのですね。

Takashi君、実は八股停留所付近には、松電の電車が走っていた当時を偲ぶものがあるのですが、分かりますか?

現在の愛媛県庁は昭和4〔1929〕年に建設されましたから、松電の時代より後のことですよね。何があるのだろう?


Takashi君、これを見たことはありませんか?



あっ!NTT西日本のところにありますね。この石碑の前を通ったことがあります。

そうです。この場所にも歴史があります。現在のNTT西日本に至るまでの変遷についてお話しします。
松山中学校跡の変遷


松山中学校は、松山藩の藩校として知られる明教館の流れを汲む学校です。その変遷を年表風にまとめてみましょう。
- 明治 5〔1872〕年 学制公布。旧明教館に松山県学校を開設。
- 明治 6〔1873〕年 英学舎と改称。
- 明治 8〔1875〕年 愛媛県に移管し、英学所と改称。
- 明治 9〔1876〕年 愛媛県変則中学校と改称。
- 明治10〔1877〕年 愛媛県北予変則中学校と改称。
- 明治11〔1878〕年 愛媛県松山中学校と改称。※ この年を創立年としている。
- 明治17〔1884〕年 愛媛県第一中学校と改称。
- 明治20〔1887〕年 愛媛県第一中学校を廃校。
- 明治21〔1888〕年 〔私立〕伊予尋常中学校を開校。
- 明治25〔1892〕年 〔私立〕伊予尋常中学校を廃校。愛媛県尋常中学校を開校。
- 明治32〔1899〕年 愛媛県松山中学校と改称。
- 大正 5〔1916〕年 持田町へ移転。※ 昭和24〔1949〕年に愛媛県立松山東高等学校と改称。

松山東高校の前身なんですね。それにしても学校の名称が頻繁に変わっていますね。

夏目漱石が英語教師として松山に赴任したのは明治28〔1895〕年4月のことですから、その時の校名は愛媛県尋常中学校ですね。

二番町の愚陀仏庵で正岡子規と同居生活を送った時ですね。以前教えていただきました。

【参考】正岡子規『散策集』吟行の道をたどろう!道後湯之町へ①
【参考】正岡子規『散策集』吟行の道をたどろう!道後湯之町へ②
【参考】正岡子規『散策集』吟行の道をたどろう!道後湯之町へ③

そうでしたね。明治28〔1895〕年10月6日に正岡子規と道後湯之町へ行き、吟行を行ったのでしたね。Takashi君、夏目漱石はどのくらい松山にいたと思いますか?

3年くらいは松山で教師生活を送ったのではないですか?

いいえ、たった1年のことでした。漱石は明治29〔1896〕年に熊本市の第五高等学校に英語教師として赴任し、さらに明治33〔1900〕年には英語教育法研究のためにイギリスへ留学しています。

そうですか。たった1年間だけ松山にいたときの行動が分かるというだけでも『散策集』はキセキの書ですね!

そうですね。Takashi君、松山中学校が持田町へ移転したあと、跡地はどのようになったと思いますか?

すぐにNTT西日本になったわけではないと思いますから、何か別の施設がつくられたのですよね。

その通りです。大正8〔1919〕年3月、日本赤十字社愛媛支部病院が現在の松山東雲学園の場所から新築移転してきたのです。
【参考】廃線隧道【BLOG版】松山電気軌道⑤【八股〜一番町】 ※ 日赤病院の宿舎が掲載された絵葉書が最後に掲載されています。

松山東雲学園の場所にあった病院といえば、正岡子規が『散策集』に記載した”病院下”の由来となった病院ですね。

正岡子規の時代は県立松山病院でしたけどね。日本赤十字社愛媛支部病院の沿革をまとめておきましょう。
- 大正 2〔1913〕年 現東雲学園がある場所に設立。
- 大正 8〔1919〕年 松山中学校跡に移転。
- 昭和22〔1947〕年 現在地〔愛媛大学東側〕に移転。

NTT西日本はいつこの場所に会社を設立したのでしょうか?

NTTというのは民営化されてからの名称で、それ以前は日本電信電話公社という社名でした。日本電信電話公社が四国電気通信局を設立したのは昭和37〔1962〕年のことです。

それが、現在のNTT西日本に繋がっているということですね。

そういうことです。さて、廃線跡をたどる旅を続けましょう。

② 裁判所前停留所付近 〜道路及び軌道の直線化〜

松電の電車が次に停車したのは、裁判所前停留所です。ここは現在の県庁前駅とほぼ同じ場所ですが、時代によっては「商品陳列所前」という名称だったこともあるようです。

この付近が、先ほど緩やかなカーブがあると指摘した場所ですね。


そうです。この場所です。道路及び路線の直進化について、『伊予鉄が走る街 今昔』の記述を引用します。
道路及び路線の直線化について
松山は昭和20年〔1945〕7月26日に米軍の空襲を受け、市街地の主要部が焼失した。その翌年の写真を見ると、なおも焼け跡が広がっている。複線の軌道が、左〔東〕の方で曲がっている。当時は、裁判所前の道幅が非常に狭く、城南線は、その部分だけが、単線になっていた。〔中略〕裁判所前の道路が拡幅された後、昭和24年〔1949〕3月、一番町-県庁前間は、軌道が道路中央に移設されて、複線化され、かつ直線化された。
『伊予鉄が走る街 今昔』 ※ 下線及び太字は引用者による

先生、この写真で裁判所はどの辺りにありますか?

航空写真に記してみますね。周囲にある建物の名称も加えましょう。


なるほど。これで位置関係はわかりました。でも現在の県庁前駅は愛媛県庁別館の前にありますから、停留所の名前は「商品陳列所前」の方が合っているかもしれませんね。

確かにそうかもしれませんね。

先生、商品陳列所跡というのはどういうことでしょうか?

商品陳列所はもともと「愛媛県物産陳列場」という名称で、地方経済の振興を目的として明治13〔1880〕年に県庁内に開設されました。大正10〔1921〕年に「商品陳列所」と改称され、さまざまなイベントが開催されていましたが、愛媛県庁本館への類焼を恐れて、昭和20〔1945〕年に取り壊されたそうです。

そうでしたか。ではこの写真は取り壊されたままの時期を捉えた貴重な写真というわけですね。

その通りです。
③ 一番町停留所付近 〜生活道路として活用されている廃線跡〜

松電の電車は、次に一番町停車場に停まりました。ここには伊予鉄道の一番町駅〔昭和42(1967)年から大街道駅に改称〕もあり、乗客争奪戦が繰り広げられた場所でもあります。
【参考】廃線隧道【BLOG版】松山電気軌道⑥【一番町〜上一万】 ※ 伊予鉄と松電の電車が並ぶ駅の様子が掲載された絵葉書があります。

伊予鉄道と松電の駅が本当に隣り合わせだったんだ!ここでの乗客争奪戦は激しかったでしょうね。

ブログ「伊予歴史文化探訪」に、『坊っちゃん列車と伊予鉄道の歩み』に掲載された回想録が引用されています。この記述を見てみましょう。
明治の“一番町テーリュージョ”
やがてロマンティックな坊っちゃん列車もずんぐりした電車にとって代られ、そのうち競争相手の“デンテツ”が出現、道後行き乗客の“取りやい(取りっこ)”が始まった。両社とも駅員が手で振る鐘をガラーンガラーンと打ち鳴らし、“道後いきー、道後いきがもうすぐ発車しま〜す。お乗りの方はお急ぎ願いま〜す”と声をからしていた。
『坊っちゃん列車と伊予鉄道の歩み』 ※ 下線は引用者による

住吉町停留所と同じですね。回想に出てきた“デンテツ”とは松山電気軌道のことですよね。

その通りです。松電に対抗して伊予鉄道が電化したこともこの回想から分かりますね。

先生、いよいよあの斜め線の場所ですね。

はい。一番町停留所を出発した松電の電車はしばらく伊予鉄道と並走し、下の写真の場所から左折して、現在の松山東警察署前まで一気に斜めに北進しました。


路線の位置から考えると、両者の鉄道が並走していた頃は松電の方が北を走っていたのですね。

そうです。では、廃線跡の現況を一番町側から順に見ていきましょう。





言われなければ廃線跡だとは分かりませんね。

そうかもしれませんね。しかし、松山の歴史を今に伝えてくれる大事な場所の一つです。

そうですね。都市開発が進んで町の景観が大きく変貌したにもかかわらず、道路として残されているからこそ私たちは廃線跡だと知ることができるのですね。

その通りです。Takashi君、この廃線跡の途中に松山市の歴史を知ることができるものがあるので、紹介しますね。それはこの石碑です。


先生、これは何を記した石碑なのですか?最初に「明和の頃」とあるので江戸時代のことだとは思いますが…。

はい。これは「喜与女之碑」といいます。

「喜与女之碑」?松山市に喜与町という地名があります。これと関係があるのですか?

その通りです。碑文を読んでみましょう。
喜与女之碑 碑文
明和の頃、奇特なる一才女あり。喜与という。神仏に帰依し人に親切にして誠意あり。故に敬愛せられし信頼せらる。偶々疫病悪す。献身介抱して人を選ばず侵食忘る。神に祈誓して曰く、病者を救い給え我身を献せんと。流行漸く衰ふ。然るに自を病に犯れ遂に斃る。人々の嘆き悲しむや親を喪う如し。相寄り相謀りて小祠を造り其の徳を偲び霊を慰む。稱へて喜与大明神という。依て其の處を喜与町と稱う。爾来、徳を慕ひて病の癒えんことを祈願するもの跡を絶たず、近郊に及べり。昭和20年7月戦災に罹り、社殿鳥有に歸す。茲に新に碑を建て、其の徳を稱え、喜与町の由来する所を明にし、之を後葉に伝えんとす。

なるほど。飢饉の際に献身的に病人を看病して、自らは病に倒れてしまった女性のお話なのですね。

そうです。この女性の名前が「喜与町」という町名の由来です。

先生、戦災で消失した社殿はどうなっているのですか?

社殿のような大きなものではなく、小さな祠にすぎませんが、有料駐車場の片隅に祀られています。


本当だ。今でもお供えがきちんとされていますね。

この祠がある場所を地図で確認しましょう。

以前紹介していただいた藤野政高の頌功碑がある三宝寺の近くですね。

その通りです。今回はここまでにしましょう。次回は、六角堂停留所から終点である道後駅まで確認しますね。

はい。ありがとうございました。