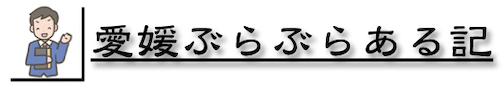大洲出身、武田斐三郎の生涯 -函館五稜郭の設計者-


写真の顕彰碑は函館の五稜郭公園内に建てられているものです。武田斐三郎(1827〜1880)は伊予国大洲出身で五稜郭の設計を行った人物なのですが、調べてみると数多くの素晴らしい業績を残した方でした。本稿は『愛媛県史 人物』の記述等を参考とし、彼の生涯をまとめたものです。
【本稿の構成】
第1章 武田斐三郎の生涯
- 誕生
- 大阪適塾、そして江戸へ…
- 函館
- その後の人生
第2章 箱館戦争の終焉 その足跡を辿る

第2章では、函館旅行の際に探索した箱館戦争の足跡を辿った記録をご紹介します。それでは始めましょう。
第1章 武田斐三郎の生涯
1.誕生
文政10(1827)年9月15日、大洲中村で藩士武田勘右衛門敬忠の次男に生まれた。通称斐三郎〔あやさぶろう〕、字成章〔しげあや〕、号竹塘〔ちくとう〕。藩校明倫堂に入学する傍ら山田東海に儒学・漢詩を学んだ。
※ 『愛媛県史 人物』より引用。名前の読み方は引用者が加筆した。

武田家の先祖は甲斐武田氏の出で、初代大洲藩主加藤貞泰の父、加藤光泰が甲斐を領した際に召し抱えられたものと考えられています。武田斐三郎が生まれた大洲中村は肱川の北方〔肱北地区〕に形成された城下町でした。

大洲城は中世の頃には宇都宮氏の居城でしたが、天正13(1585)年の豊臣秀吉の四国平定後、伊予国の領主となった小早川隆景の城郭整理によって在城として位置付けられると、その後城主となった戸田、藤堂、脇阪氏の代によって近世城郭へと徐々に整備されていきました。


城下町は大洲城のある南側(肱南地区)と肱川を挟んだ北側(肱北地区)に分かれ、それぞれ中央部には往還が通り、それらは肱川の「渡し」によって結ばれていました。肱南側は南へ延びる宇和島往還、西へ延びる八幡浜往還の起点に、肱北側は北へ延びる松山往還の起点になっていました。これらを現在の地図に当てはめてみましょう。


大洲市ホームページに、武田斐三郎の生家跡に建てられた碑が掲載されていました。ホームページをご覧ください。
【参考】武田敬孝・成章兄弟誕生地 ーわがまちの文化財ー 大洲市ホームページ

現地を訪れてみましたが、新しい住居が建設されていて、碑は取り除かれてしまっていました。残念です。地図を掲載しておきますが、個人宅がありますので訪れる際はお静かに願います。

さて、武田斐三郎は大洲藩校の明倫堂にて儒学・漢詩を学びつつ、母親の実家で漢方医学を学んでいましたが、医学への興味・関心が高まり、藩主加藤泰幹に大阪の適塾で学びたいと願い出たそうです。斐三郎22歳の時でした。
2.大阪適塾、そして江戸へ…
弘化5(1848)年大坂に赴き緒方洪庵の適塾に入門、嘉永3(1850)年には江戸に留学して伊東玄朴や佐久間象山に学んで洋学・兵学を修得した。
※ 『愛媛県史 人物』より引用。西暦は引用者が加筆した。

適塾は緒方洪庵が大阪船場に開いた蘭学の私塾で、福沢諭吉、大村益次郎、大鳥圭介、高松凌雲、高峰譲吉など幕末から明治にかけて活躍した多くの名士を輩出しました。その建物は「緒方洪庵旧宅および塾」として国の史跡に、「旧緒方洪庵住宅」として重要文化財に指定され、現在は大阪大学が管理をしています。



適塾で学んだ2年の間に頭角を表した斐三郎は塾頭を務め、緒方洪庵の紹介で伊東玄朴や佐久間象山に兵学・砲学まで学んだそうです。
【参考】wikipedia 伊東玄朴 :幕末から明治にかけての蘭方医。江戸幕府まで登り詰めた。
【参考】wikipedia 佐久間象山:江戸時代後期の松代藩士、兵学者、種子学者、思想家。

嘉永6(1853)年6月3日、浦賀沖にペリー艦隊が来航して幕府に開国を要求するという大事件が勃発します。この時、斐三郎は佐久間象山に連れられて吉田松陰らと共に浦賀に行き、黒船を目撃してその見聞を『三浦見聞記』としてまとめます。斐三郎27歳の時でした。

この時の様子は、昭和52(1977)年放送の大河ドラマ『花神』で描かれていましたね。さて、翌嘉永7(1854)年、再び来航したペリーは江戸幕府と日米和親条約を締結します。条約の内容を確認しておきましょう。この時の決定が斐三郎の運命を大きく変えていくことになります。
日米和親条約
第1条 日米両国・両国民の間には、人・場所の例外なく、今後永久に和親が結ばれる。
第2条 下田と箱館を開港する。この2港において薪水、食料、石炭、その他の必要な物資の供給を受けることができる。物品の値段は日本役人がきめ、その支払いは金貨または銀貨で行う。
第3条 米国船舶が座礁または難破した場合、乗組員は下田または箱館に移送され、身柄の受け取りの米国人に引き渡される。避難者の所有する物品はすべて返還され、救助と扶養の際に生じた出費の弁済の必要は無い(日本船が米国で遭難した場合も同じ)。
第4条 米国人遭難者およびその他の市民は、他の国においてと同様に自由であり、日本においても監禁されることはないが、公正な法律には従う必要がある。
第5条 下田および箱館に一時的に居留する米国人は、長崎におけるオランダ人および中国人とは異なり、その行動を制限されることはない。行動可能な範囲は、下田においては7里以内、箱館は別途定める。
第6条 他に必要な物品や取り決めに関しては、両当事国間で慎重に審議する。
第7条 両港において、金貨・銀貨での購買、および物品同士の交換を行うことができる。交換できなかった物品はすべて持ち帰ることができる。
第8条 物品の調達は日本の役人が斡旋する。
第9条 米国に片務的最恵国待遇を与える。
第10条 遭難・悪天候を除き、下田および箱館以外の港への来航を禁じる。
第11条 両国政府が必要と認めたときに限って、本条約調印の日より18か月以降経過した後に、米国政府は下田に領事を置くことができる。
第12条 両国はこの条約を遵守する義務がある。両国は18か月以内に条約を批准する。

条約の締結後、開港が決定した下田・箱館はその準備が開始されます。斐三郎は著書『三浦見聞記』を読んだ幕閣からその才能を認められ、旗本格として幕府に出仕することになりました。この頃、アメリカとの条約締結を聞きつけた諸国が幕府に開国を迫り、同様の和親条約を締結しています。その国とは次の3ヵ国です。
◉ オランダ ⇨ 日蘭和親条約(1856) 締結場所:長崎
◉ イギリス ⇨ 日英和親条約(1854) 締結場所:長崎
◉ ロシア ⇨ 日露和親条約(1855) 締結場所:下田

斐三郎は、箕作阮甫に従い、長崎で行われたロシアのプチャーチンとの交渉に参加し、通詞御用を務めます。斐三郎28歳の時でした。
【参考】wikipwdia 箕作阮甫:蕃書調所の主席教授を務め、現在の東京大学の基礎を作った蘭学者。
【参考】wikipedia プチャーチン:ロシア帝国の海軍軍人

さて、日露和親条約は、日本が諸外国に対して初めて国境を画定させた条約でもあります。条約の内容を確認しておきましょう。
日露和親条約
◎ 千島列島における、日本とロシアとの国境を択捉島と得撫島の間とする。
◎ 樺太においては国境を画定せず、これまでの慣習のままとする。
◎ ロシア船の補給のため箱館、下田、長崎を開港する。
◎ ロシア領事を日本に駐在させる。
◎ 裁判権は双務に規定する。
◎ 片務的最恵国待遇。

江戸に戻った斐三郎は、幕府の命で箱館奉行・堀利熙らの蝦夷地・樺太巡察に随行、箱館でアメリカのマシュー・ペリーと会談しました。現在、函館市の元町公園内に「ペリー提督来航記念碑」と「ペリー提督像」が建立されています。




この時の巡察中に箱館奉行所が設置されると箱館詰めとなり、斐三郎は10年間同地に滞在することになりました。なお、安政5(1858)年に江戸幕府がアメリカ・オランダ・イギリス・フランス・ロシアと修好通商条約をそれぞれ締結したのち、翌年から開港した箱館・長崎・下田において諸外国との貿易が本格的に始まることになります。
3.箱館へ
安政3(1856)年洋学塾設立の建言が入れられて、箱館奉行諸術調所の教授になり、蘭学をはじめ聞きかじりの英・露語で語学、航海術、測量術、砲術などを教え、山尾庸三・前島密・井上勝・新島襄など全国から箱館に馳せ参じた若き学徒を指導した。同年弁天崎砲台を着工、更にオランダ式築造術を駆使して元治元年(1864)五稜郭を完成させた。五稜郭は我が国最初の西洋式城郭で、五稜星型の土塁からこの名が付けられた。箱館奉行小出秀実が居城したが、戊辰戦争の際幕臣榎本武揚らがここに拠り,新政府軍に抗戦したことはよく知られている。
※ 『愛媛県史 人物』より引用。西暦は引用者が加筆した。

箱館に滞在中の斐三郎の活躍も物凄いですね。彼が指導した人々は、いずれも日本の近代化になくてはならない人物です。彼らが残した業績を一人一人紹介します。
① wikipedia 山尾庸三:江戸末期に長州藩に生まれ、伊藤博文・井上馨らとともに秘密留学生としてロンドン留学を行う。明治になり伊藤博文と工部省の設立に尽力。
② wikipedia 前島密 :日本の近代郵便制度の主要な創設者の一人。「日本近代郵便の父」といわれる。
③ wikipedia 井上勝 :明治期の日本の鉄道官僚。鉄道発展に寄与し、「日本の鉄道の父」といわれる。
④ wikipedia 新島襄 :幕末から明治時代の教育者・クリスチャン。京都に同志社英学校〔現同志社大学〕の設立に寄与。

そして、五稜郭および弁天崎砲台の築造です。まずは五稜郭の特徴を確認しましょう。
五稜郭


この場所に五稜郭を築造するに至った経緯について、箱館奉行所のパンフレットから引用します。
五稜郭築造の経緯
箱館奉行所は、幕末の箱館開港により設置された江戸幕府の役所です。安政元(1854)年の日米和親条約により、箱館と下田が開港され、箱館山麓(現在の元町公園)に奉行所が置かれました。しかし、港湾から近く防備上不利であったことなどから、内陸の亀田の地に奉行所を移すことになりました。奉行所を守る外堀には、箱館奉行所諸術調所教授役で蘭学者の武田斐三郎が、ヨーロッパの城塞都市を参考とした西洋式の土塁を考案し、星形五角形の形状から五稜郭と呼ばれるようになりました。
※ 五稜郭跡が見えるよう、左下方向に少しずらしてからご覧ください。

「元町」という地名は、箱館の旧市街地であったことから付けられたものです。そして函館湾は現在のJR函館駅西部に位置するので、奉行所が湾内から至近かつ遮るものがなく、諸外国が開戦に及べば一撃で粉砕される恐れがありました。さらに外国人の遊歩区域内の箱館山に登れば奉行所を眼科に見下ろすことができ、役所をはじめとした要地の配置が筒抜けでした。では、亀田の地が適切であると判断した理由は何だったのでしょうか。


上の地図は、江戸時代後期の大砲の射程距離を函館の地図に当てはめたものです。これを見ると、函館湾内からの艦砲射撃の射程外に五稜郭を建設したということが分かりますね。また、色別標高図で見てみると、五稜郭がやや高い場所に建てられていることが分かります。つまりこの場所からは函館湾が視認できるだけでなく、外国船の動向が伺いやすいという特徴が見て取れます。
【参考】国土地理院電子国土基本図〔色別標高図〕:函館 ☜クリックしてご覧ください。

下の2枚の写真は一本木関門付近の解説柱に添付してあった古地図を撮影したものですが、五稜郭から一本木関門までの区間には建物がほとんど描かれておらず原野であり、当時は箱館の町や箱館山を見通すことができたと思われます。



以上のことから亀田の地を建設場所と定め、安政4(1857)年から五稜郭の築造が始まりました。完成は元治元(1864)年のことです。それでは次に、五稜郭に見られる防御の工夫を確認しましょう。
五稜郭 防御の工夫
① 高い建物を作らない

戦国時代に築かれた城には高い天守が建てられ、それは力の象徴でもありました。しかし、このように目立つ高い建物は狙われやすく、大砲によりすぐに破壊されてしまいます。そこで五稜郭には高い建造物は造らなかったようです。大洲城と五稜郭の写真を並列してみます。



五稜郭の中で最も高い建物は箱館奉行所ですが、大洲城天守と比べて高さが全然違います。これには大砲の攻撃から守るという考えがあったのですね。
② 広い敷地の確保

これも大砲による攻撃を意識してのことですが、広い敷地を確保し、建物は中央部に配置するようにしています。

③ 石垣よりも土塁を多用

石垣は大砲の攻撃によって破壊された時に破片が周囲に飛び散り危険であるため、攻撃の威力を吸収できる土塁を多用しています。
④ 防御力が高い星形を採用

五角形の先の部分を「稜堡〔りょうほ:外に向かって突き出した角の部分〕」といいますが、稜堡には死角がなく、両サイドから攻撃できるため、侵入する敵に十字砲火を浴びせることが可能です。


さらに、入り口付近には出入り口を防御するために半月堡も設けました。


半月堡には、防御のための数々の工夫が見られます。解説板の文章を読んでみましょう。


「刎ね出しの石垣」とありますが、これのことです。


高床倉庫に鼠返しというものが設けられていますが、用途としては同じです。これがあることで、石垣を登ろうとする敵を防いでいるのです。また、周囲にはこんな工夫が見られます。


この写真は半月堡の上から堀の方向を撮影したものです。石垣と堀との間の土地がやや高くなっていますね。これは半月堡からの死角をなくすために意図的に土塁を築いて土地を高くし、攻撃をしやすくするための工夫です。土地の起伏が多いというのも、五稜郭の防御上の工夫なのです。
弁天崎砲台

次は弁天崎砲台です。これは箱館港に出入りする外国船に対抗するための海防強化策の一環として、以前築かれていた台場を大型の洋式多角形砲台に改築したものです。その場所について、一本木関門に設置された解説柱に掲示してある古地図を再度見てみましょう。



左の図では「辨天台場」、右の図では「台場」と記されているのが弁天崎砲台です。橋によって元町と繋がっていたことが図から分かります。弁天台場は現在の函館ドック付近にあったようですが、明治29(1896)年の港湾改良のために取り壊され、周囲が埋め立てられてしまいました。当時の様子を知るには、函館市内にある史跡の解説板の写真などで確認するしかありません。

【参考】wikipedia 弁天台場
箱館におけるその他の業績

箱館詰めの間、武田斐三郎はさらに多くのことを成し遂げています。ちょっとご紹介しましょう。
◉ 溶鉱炉の建設(33歳)
◉ 生徒らを連れて国産帆船「亀田丸」を操船して日本一周(33歳)
◉ ロシアの黒竜江に日本初の修学旅行を兼ねた貿易に出かける(35歳)

このように、さまざまな業績を残した武田斐三郎は、五稜郭の完成後、幕府の要請により江戸に戻りました。
4.その後の人生
元治元(1864)年五稜郭完工を見て箱館を去って江戸に帰り、開成所教授・関口大砲製造所頭取に任ぜられ、王子反射炉を建設し慶応3(1867)年にはナポレオン砲の国産化に成功した。明治維新後、新政府の兵部省に出任して、大阪兵学寮教授・幼年学校長などを勤めて陸軍士官の養成に当たった。明治13(1880)年1月18日52歳で没した。遺体は儀仗兵に守られて、浅草新谷町智光院境内の墓地に葬られた。著書に『蝦夷入北記』『黒龍江記事』『洋貨考』などがある。特別史蹟函館五稜郭には「竹塘武田成章先生」碑が建立されて肖像レリーフが刻まれ、城内函館博物館に斐三郎の資料が展示されている。
※ 『愛媛県史 人物』より引用。西暦は引用者が加筆した。

江戸に戻っても武田斐三郎が身に付けた知識・技術は各所から必要とされました。明治の世でもそれは続き、明治8(1875)年には陸軍士官学校を開校させましたが、日本陸軍創設の過酷な仕事で健康を害してその生涯を閉じました。彼の業績を讃えるため、昭和39(1864)年7月、五稜郭に「武田斐三郎先生顕彰碑」が建立されています。また、五稜郭タワー内にも斐三郎像がありました。



「武田斐三郎先生顕彰碑」のレリーフ部分は顔と頭だけが光り輝いていますね。これは彼の頭の良さにあやかろうと、訪れた観光客がこの部分を撫で続けた結果だそうです。私自身も「頭がもっと良くなれ…」と念じながら撫でさせてもらいました。さて、武田斐三郎の生涯についての話はここまでです。それでは次に、函館市内に残る箱館戦争の足跡を紹介していきます。
第2章 箱館戦争の終焉 その足跡を辿る

箱館戦争とは、慶応4(1868)年1月3日〔旧暦〕に始まった鳥羽伏見の戦いから始まる戊辰戦争〔旧幕府軍と新政府軍との戦い〕の最後の戦いのことをいいます。箱館戦争の経緯を年表にまとめたのでご覧ください。


年表中の①〜⑥は、函館旅行中に取材・撮影をした史跡を指しています。函館市内には箱館戦争関連の史跡が多数あり、観光地としてきちんと整備されていました。これらの場所を地図に表してみましょう。


それでは撮影した写真とともに現地の様子を確認していきましょう。
① 特別史跡 五稜郭跡

五稜郭の全貌と防御の工夫は上にまとめていますので、五稜郭内にあるものを紹介していきましょう。
【箱館奉行所】


箱館奉行所は、もともと蝦夷地の統治や開拓、開港地箱館での諸外国との交渉など幕府の北方政策の拠点でしたが、箱館戦争時には榎本武揚ら蝦夷共和国の政治・外交拠点となりました。箱館戦争終結後、明治4(1871)年に開拓使により解体されましたが、平成22(2010)年に復元され現在に至ります。一番高い所にあるのが刻を知らせる太鼓櫓ですが、道後温泉本館の建物とよく似ていますね。


箱館奉行所の刻を知らせる太鼓の音や叩き方はどうだったのでしょうか?ちなみに、道後温泉本館の刻太鼓はこういう音です。動画をご覧ください。
【大砲】

ブラッケリー砲とクルップ砲の2基が展示されていました。これらはいずれも箱館戦争時に旧幕府軍が使用していたものです。
【一本松の土饅頭】


武田斐三郎先生顕彰碑を過ぎて真っ直ぐ進んだ所にあります。土方歳三と伊庭八郎が戦死後に運ばれ、最初に埋葬された場所ではないかとの伝説があるそうです。明治11(1878)年の土塁修復工事の際に発見された夥しい遺体と共に願乗寺へ改葬されました。願乗寺はその後幾度か火災に見舞われていますので、遺体がその中にあったかどうかは分かりません。
【兵糧庫】


五稜郭築造当時の建物で、唯一現存している建物です。訪れた時にいただいた資料によれば、当初は土蔵造りであったものが後世に板張りに変えられたそうです。丁度建物内で展示が行われていたので、箱館戦争関係の資料を拝見することができました。撮影してもよかったので、展示品の一部をご紹介します。
【参考】箱館奉行所 公式ウェブサイト
② 新撰組屯所跡(旧称名寺)


函館元町ホテルの南側にあります。箱館戦争当時この場所には称名寺があり、箱館警備の任に就いた新撰組の屯所がありました。解説板の文章を読んでみましょう。


解説板に記されている「現在ある称名寺の供養碑」はこれです。

境内には、択捉航路の開発や北方漁場の経営、江戸幕府の代理人としてロシアとの交渉に当たったことでも知られる高田屋嘉兵衛の顕彰碑もありました。

【参考】高田屋顕彰館・歴史文化資料館ホームページ:高田屋嘉兵衛について

新撰組に話を戻します。弁天台場跡付近に新撰組関係の史跡がいくつかありましたので紹介します。

弁天台場は明治29(1896)年の港湾改良時に取り壊され、周囲が埋め立てられたので、昔の姿を見ることはできません。しかし、港湾改良の際に弁天台場の石垣が防波堤に転用されました。この石垣は今も見ることができ、碑も建てられています。

石垣を撮影してきました。土木学会選奨土木遺産にも認定されている素晴らしい石垣です。どうぞご覧ください。







③ 土方歳三最期の地碑


J R函館駅から徒歩約10分の所にあります。碑の側に解説板がありましたので、土方歳三戦死までの経緯を確認しましょう。


五稜郭タワー内に出陣する土方歳三のミニチュア模型がありますが、実際はどうだったのでしょうね。


一本木関門が当時あった場所を古地図で確認しておきましょう。



土方歳三が戦死した場所については、ほかに鶴岡町(現在の大手町付近)や、栄国橋(異国橋。現在の十字街付近)など諸説あります。栄国橋があった場所の近くに解説板がありましたので、見ておきましょう。

栄国橋があったとされる交番は、函館市電十字街停留所のすぐ近くにありました。


函館市電十字街停留所の位置を地図で確認しておきましょう。戦死した場所とされる大手町も検索してみてください。
④ 千代台公園

千代台公園は野球場・弓道場・陸上競技場・庭球場・プールを備えた運動公園ですが、この場所にはもともと択捉などの出張陣屋の元陣屋としての役割を持つ千代ヶ岡陣屋がありました。古地図では「津軽陣屋」と記されています。



安政2(1855)年以降、幕府が箱館の警備を津軽藩に命じたことから「津軽陣屋」と呼ばれるようになったのですが、箱館戦争時に蝦夷共和国軍がここに兵を配置したのです。千代ヶ岡陣屋は現在の中島小学校付近から千代台公園野球場にかけての範囲にあり、東西約130m、南北約150mの土塁が築かれていたそうです。陣屋があった場所を現代の地図で確認しましょう。

明治2(1869)年5月16日、ここで箱館戦争最後の戦いが行われ、責任者であった中島三郎助らは壮烈な最期を遂げました。戦死した中島三郎助父子の慰霊碑がすぐ近くに建てられています。
⑤ 中島三郎助父子最期の地碑


碑の側に建てられている解説板に中島三郎助の人生が記されています。読んでみましょう。


「浦賀奉行配下の役人」とありますが、中島三郎助は嘉永6(1853)年6月のペリー来航の際、副奉行と称して通訳ともに旗艦「サスケハナ号」に乗船しただけでなく、アメリカ側使者の応対も行った人物です。そう考えるとこの人はすごい人ですね。
⑥ 亀田八幡宮


榎本武揚らはこれ以上の戦闘は不可能と判断し、降伏することを決定しました。5月17日、蝦夷共和国側の榎本武揚、大鳥圭介と新政府軍の黒田清隆が降伏の誓約書を交わしたのが亀田八幡宮の旧拝殿です。現在この場所には「箱館戦争降伏式之地」碑が建立されています。


何と、碑銘の揮毫は榎本武揚の曾孫である榎本孝充さんでした!旧拝殿には箱館戦争時の弾痕が残っているとのことですが、撮影するのを忘れてしまいました。近いうちに再度函館を訪れよう。
⑦ 函館市内に建つ像

本稿の最後に、今回の函館旅行で撮影した歴史上の人物の像を紹介します。函館を訪れる機会があれば、みなさん自身の目でこれらの像をみてくださいね。
【土方歳三】
【榎本武揚】
【高田屋嘉兵衛】

今回の函館旅行で訪れた史跡の場所をもう一度地図で確認しておきましょう。


本稿は以上です。2泊3日の函館旅行でしたが、まだまだ訪れなければならない場所があります。近日中に都合をつけ、再訪したいと思います。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。