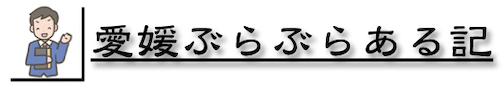二宮金次郎像探索の旅 番外編Part.3 函館をゆく!


函館市内において5体の二宮金次郎像の存在を確認しています〔令和7年8月現在〕。調査結果を表にまとめましたのでご覧ください。

現在、二宮金次郎像が建つ小学校〔閉校した学校も含む〕名は次のとおりです。
- 函館市立中部小学校
- 函館市立新川小学校跡地
- 函館市立弥生小学校
- 函館市立亀雄小学校跡地
- 函館市立蛾眉野小学校跡地

先日、函館を訪れた際、3体の二宮金次郎像を撮影してきました。本稿では、その3体の二宮金次郎像を紹介します。
1 函館市立中部小学校

【学校の沿革】 ※ 参考:wikipedia
昭和53(1978)年 新川小学校と松風小学校を統合し、開校。
平成12(2000)年 肢体不自由特殊学級閉級
平成14(2002)年 学校週5日制導入。弱視特殊学級開級

正門のすぐ側に建てられていました。さまざまな角度から像を撮影しましたので、ご覧ください。






台座の銘文は「勤倹力行(きんけんりっこう)」。しっかりと働いて、質素に暮らしながら力の限り努力することという意味です。
◉ 「勤倹」:よく働いて、無駄遣いをしないようにすること。
◉ 「力行」:力の限り努力すること。

像が建立されたのは昭和30(1955)年9月15日。ご夫婦の金婚の賀を記念して寄贈されたようです。だとすれば、中部小学校は松風小学校の跡地につくられたのでしょうかね。そしてもう一つ。像の背後に記された「鉄堂」の文字。愛媛県内の小学校に建つ二宮金次郎像にも同じ文字が記されている像がいくつかあります。
〔新居浜市立大島小学校〕
〔西予市立周木小学校〕
2 函館市立新川小学校跡地


「あのねのブログ」によれば、昭和3(1928)年に函館市内最初の鉄筋コンクリート造りの校舎が建設されたそうで、同ブログでは「東京以北でも最初であろうといわれている」と記しています。
【参考】あのねのブログ 新川小学校跡地

台座に記された銘文は「至誠」。この上なく誠実なこと、まごころを表します。中国の古典『孟子』にある「誠は天の道なり。誠を思うは人の道なり。至誠にして動かざるものは、未だこれ有らざるなり」という言葉からとられたものです。さまざまな角度から像を撮影したので、ご覧ください。





寄贈年等を確認するために台座の裏面を撮影しましたが、背後の壁からの距離が近く、読解することができませんでした。
3 函館市立弥生小学校


ブログ「函館散歩」によれば、一番最初の弥生小学校の開校は明治15(1882)年だそうです。昭和9(1934)年の大火後、函館市内の小学校の校舎が鉄筋コンクリート造りに変わっていきますが、弥生小学校校舎は昭和13(1938)年に完成。現在は老朽化のため取り壊され、平成23(2011)年から現在の校舎になっています。なお、石川啄木が代用教員として勤務していた学校でもあります。像をさまざまな角度から見てみましょう。




台座に銘文はありませんでした。建立したのが山﨑鉄工所だというのは非常に珍しいですね。取り壊される前の校舎の写真が他ブログに掲載されていましたのでリンクさせておきます。こちらもご一読ください。
【参考】ブログ関根要太郎研究室@はこだて:函館市立弥生小学校旧校舎(函館懐かしの建築)

残り2体の二宮金次郎像については、旅程が合わずに撮影できておりません。Google mapを添付しておきますので、ストリートビューでご覧ください。
4 函館市立亀雄小学校跡地〔現函館五稜之蔵(株)〕
◉ 令和元(2019)年3月31日閉校。126年の歴史に幕を下ろしました。閉校時の生徒数は13名だったそうです。
【アクセス】
5 函館市立蛾眉野小学校跡地
【沿革】
明治35(1902)年 蛾眉野簡易教育所として開校。
昭和35(1960)年 児童数100名。この時が最大生徒数。
平成15(2003)年 創立100年目に閉校。亀雄小中学校と統合。
【参考】eHAKO 函館地域ニュースアーカイブ「蛾眉野小中学校で最後の卒業式と閉校式
【アクセス】

本稿は以上です。今回撮影できなかった2体の二宮金次郎像は、再度函館を訪れた際に撮影しようと思います。関連記事をリンクさせておきますので、合わせてご一読ください。ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
【関連記事】大洲出身、武田斐三郎の生涯 ー函館五稜郭の設計者ー